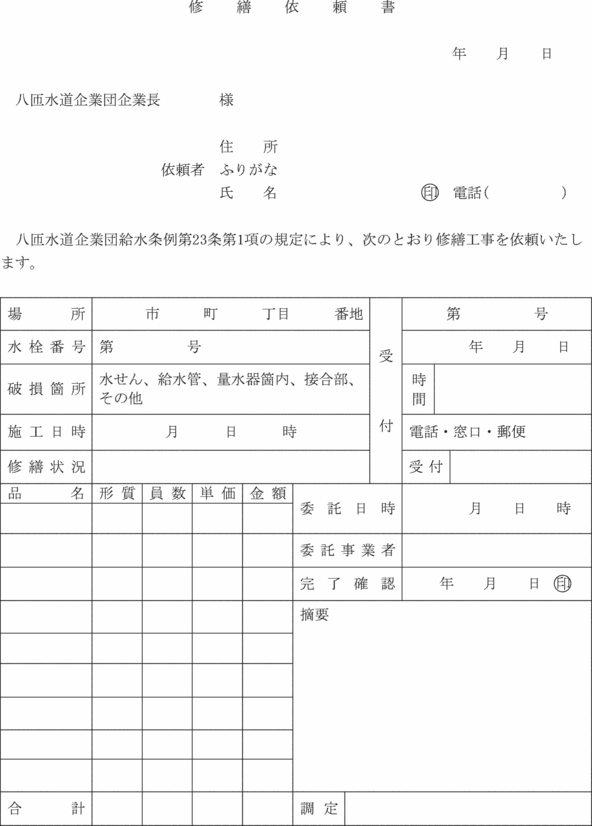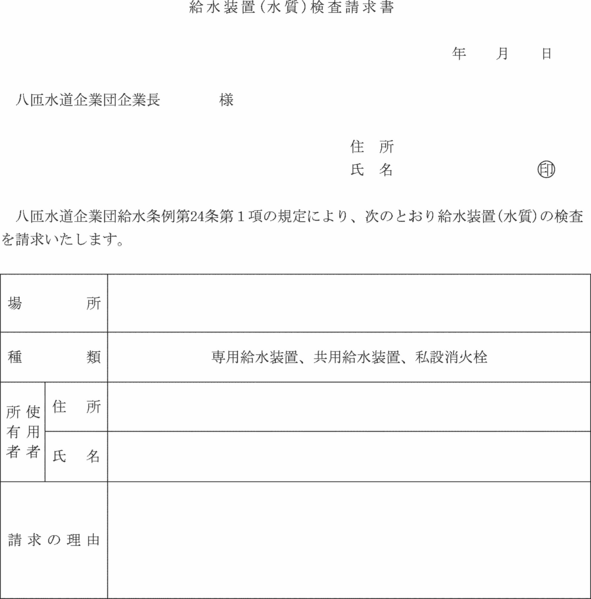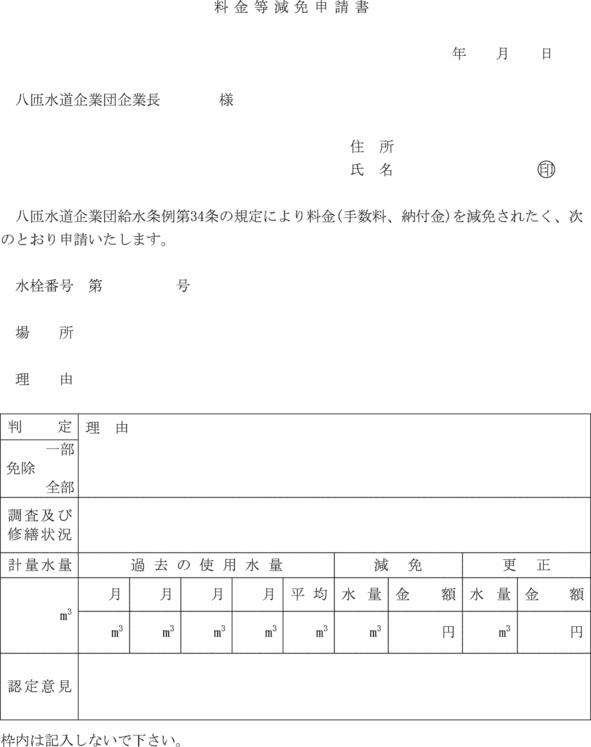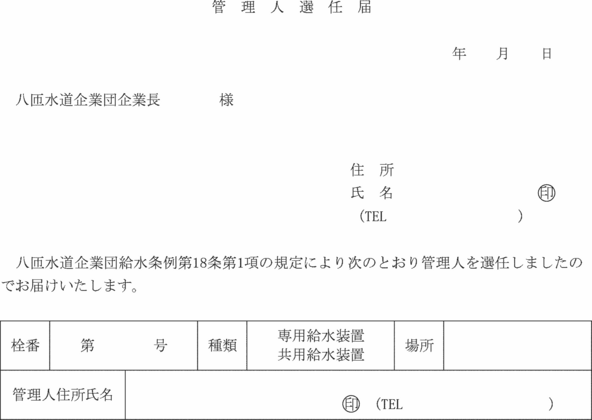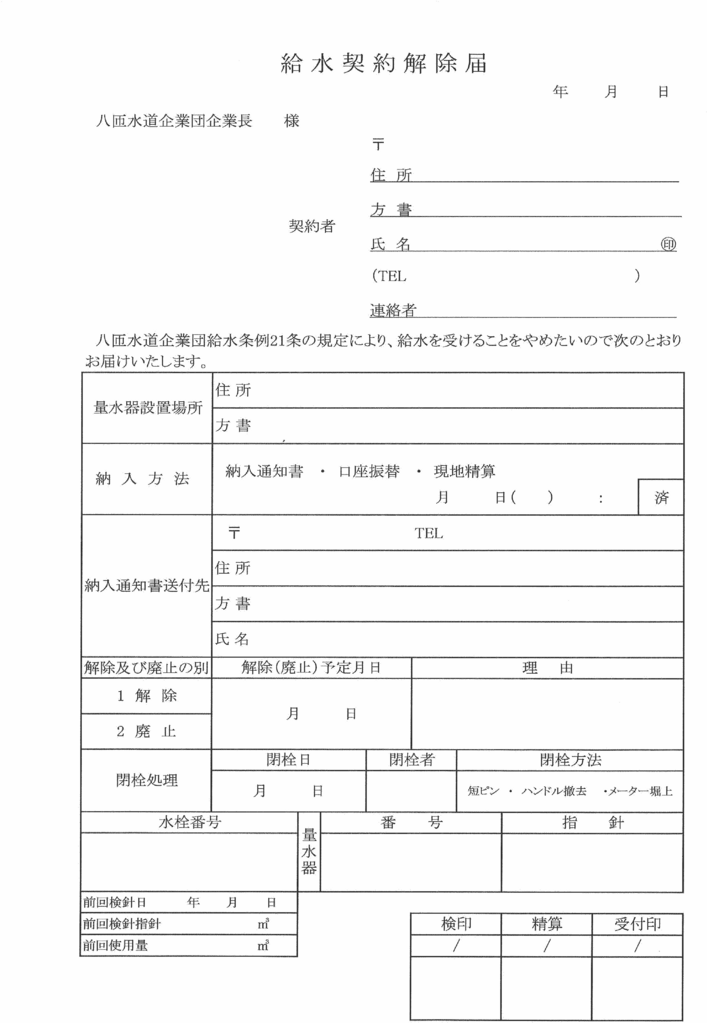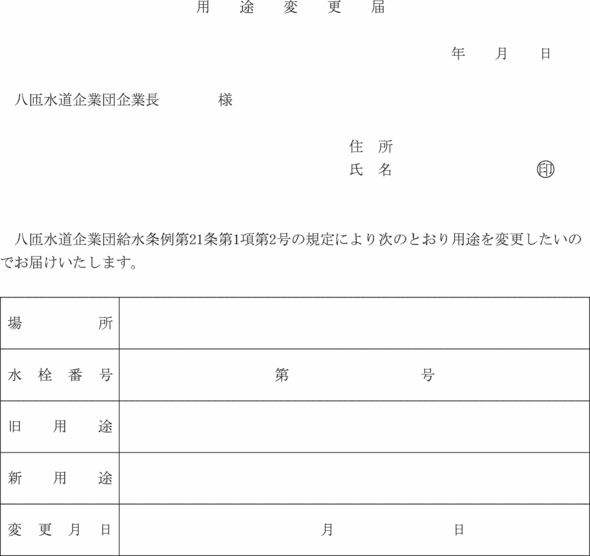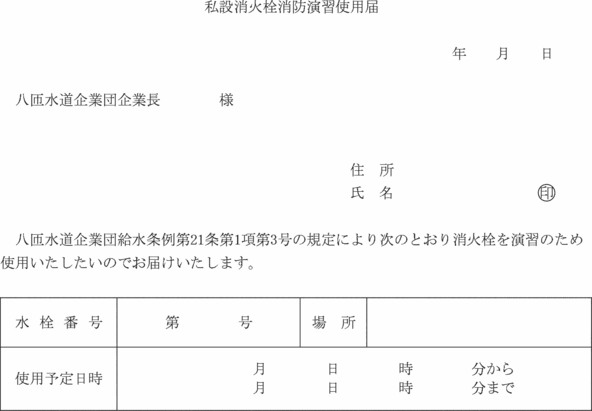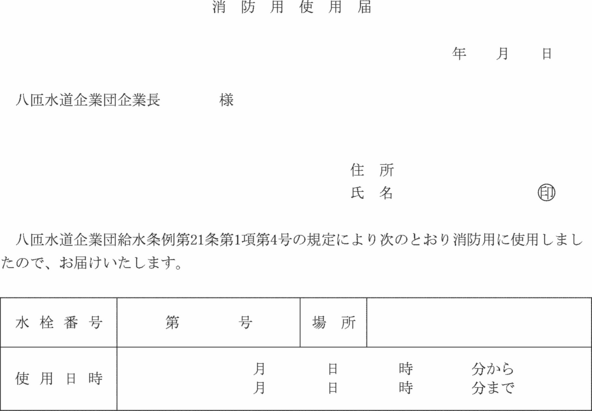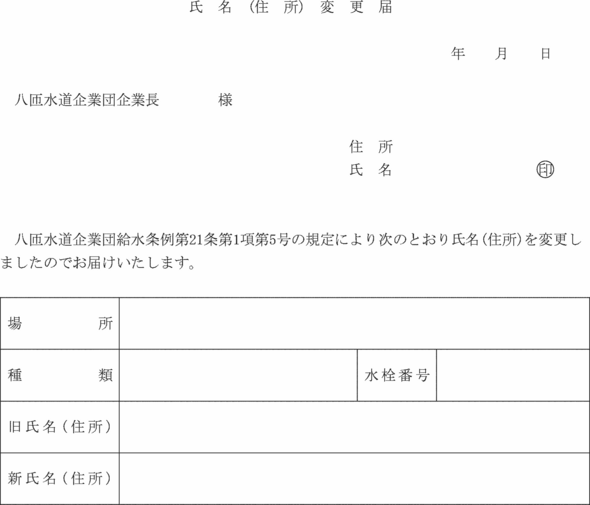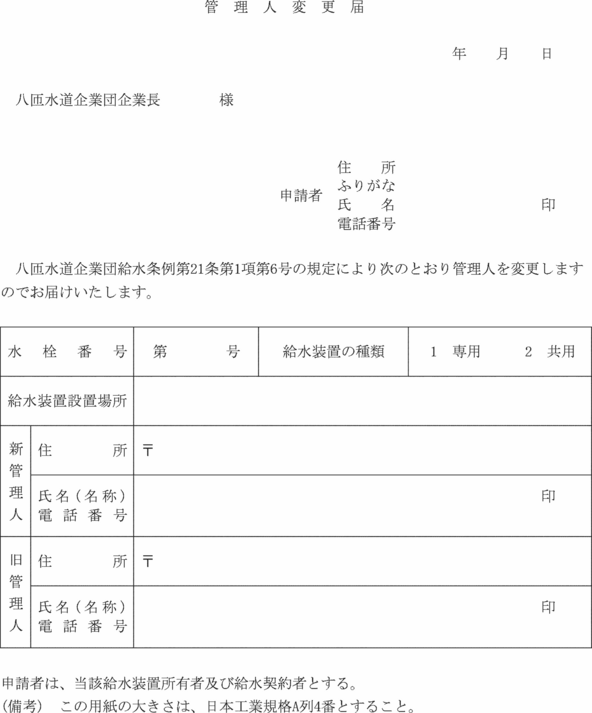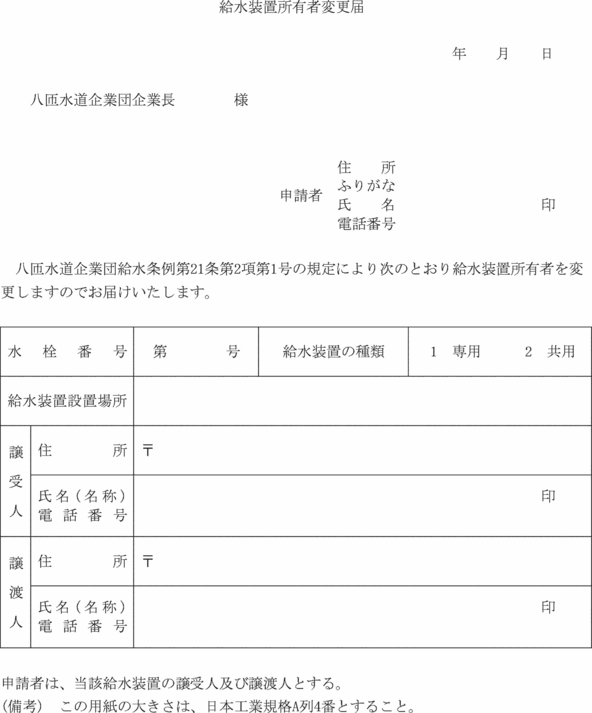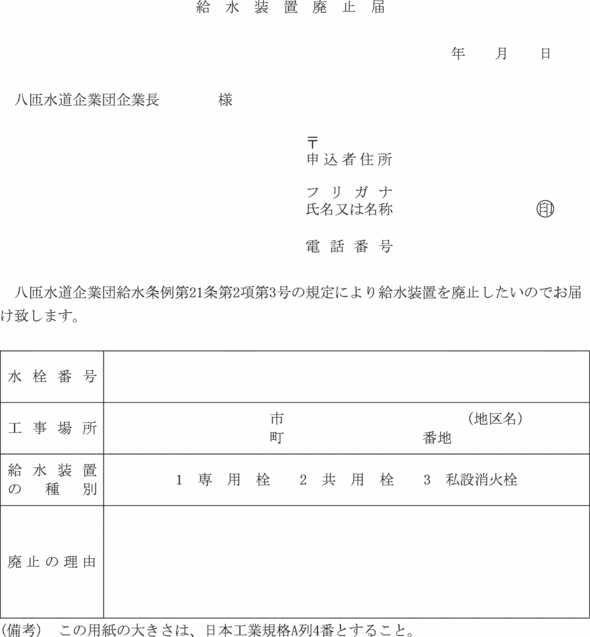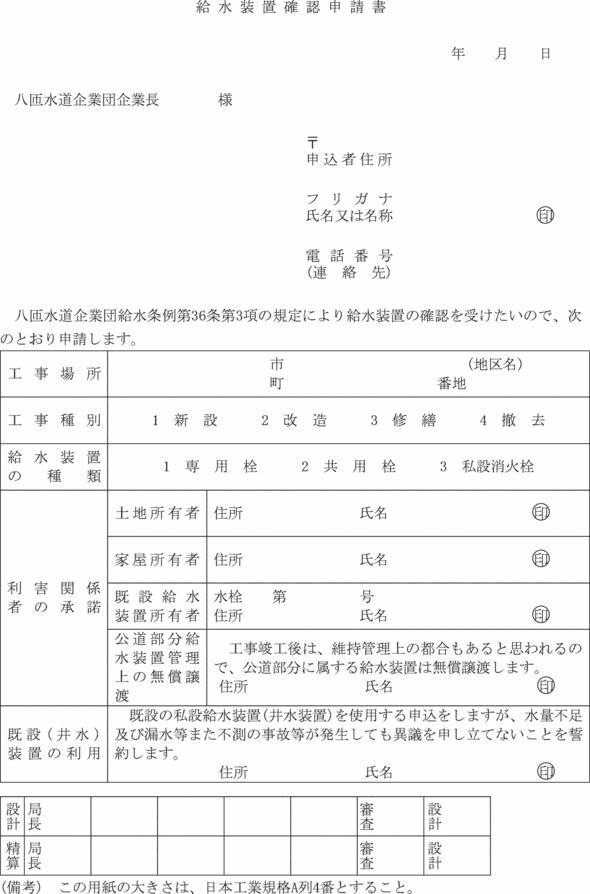○八匝水道企業団給水条例施行規程
昭和51年7月1日規程第2号
八匝水道企業団給水条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、八匝水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第43条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の承認申請)
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 給水装置工事を行う場所
(3) 給水装置の工事種別
(4) 給水装置の種類
(5) 給水装置工事を指定給水装置工事事業者に委託する者にあつては、当該指定給水装置工事事業者の名称及びその給水装置工事主任技術者の氏名
(6) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとする者にあつては、当該土地又は構築物の所有者の同意を得た旨
(7) 他人の給水装置から給水管を分岐しようとする者にあつては、当該給水装置の所有者の同意を得た旨
(8) 既設の私設給水装置を利用しようとする者にあつてはその旨
2 給水装置の新設又は改造に伴つて受水タンクを設置しようとする者は、前項の申込書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。
(給水装置工事の取消し)
第3条 条例第5条の規定により、給水装置工事の申込みをした者が、当該申込みを取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事取消届(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。なお、取消し以前に係る費用は申請者の負担とする。
(分岐引用者への通知)
第4条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。
(給水装置の構成及び付属用具)
第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもつて構成する。
2 給水装置には、水道メーター筐その他の付属用具を備えなければならない。
(分水栓の位置)
第6条 分水栓の位置は、他の分水栓の位置から30センチメートル以上離さなければならない。
(給水管径の決定)
第7条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(受水タンクの設置等)
第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他企業長が必要と認める箇所には、受水タンクを設けなければならない。
2 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。
(給水装置の材料)
第9条 給水装置に使用する材料は、衝撃、荷重、土質、凍結、侵食等の物理的、化学的条件を考慮し選定するものとする。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第10条 条例第8条第1項の規定により企業長が指定する給水管及び給水用具の構造及び材質の基準のうち、公道及び企業長の認める私道の部分に用いる給水管の材質の基準は、次のとおりとする。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(1) 口径が20ミリメートル及び25ミリメートルの給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が40ミリメートル及び50ミリメートルの給水管 ステンレス鋼管
(3) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管
(給水管の埋設の深さ)
第11条 給水管の埋設の深さは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公道内 管の上端から90センチメートル以上
(2) 私道内 管の上端から60センチメートル以上
(3) 宅地内 管の上端から30センチメートル以上
(給水管の防護措置)
第12条 給水管を水路、下水開きよ等を横断して配管する必要があるときは、伏せ越しとし、やむを得ず露出配管するときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
2 電触、衝撃又は凍結のおそれのある場所には、給水管の防護措置を講じなければならない。
3 酸又はアルカリによる侵食のおそれのあるところに給水管を配管するときは、給水管の防食措置を講じなければならない。
4 ボイラー等温度差に著しい影響を与える装置が設置されている場所に給水管を配管するときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、当該給水装置以外の水管その他水が汚染されるおそれのある設備に直接連結させてはならない。
2 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。
3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する措置を設けなければならない。
4 水洗便器に直結する給水装置にあつては、バキユームブレーカー付フラツシユバルブを備える等逆流防止の措置を講じなければならない。
(給水装置工事の設計及び施工の基準)
第14条 給水装置工事の設計及び施工については、この規程に定めるものの他別に企業長が定める基準によるものとする。
第15条 削除
(工事検査)
第15条の2 条例第6条第2項の規定により給水装置工事の工事検査を受けようとする者は、工事完成後直ちに工事検査申請書を企業長に提出しなければならない。
(給水契約の申込み)
(メーターの設置)
第17条 条例第19条第1項に規定する水道メーター(以下「メーター」という。)は、1建築物に1個とする。ただし、当該建築物が構造上2以上の部分に区分されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であつて、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとにメーターを設置することができる。
第18条 条例第19条第2項に規定するメーターの設置の位置は、次の各号に掲げる要件をそなえているものとし、当該メーターは、水平に設置しなければならない。
(1) メーターの点検及び取り替え作業が容易に行うことができること
(2) 衛生的で常に乾燥していること
(3) メーターを損傷するおそれがないこと
(メーターの管理)
第19条 メーターを設置する場所には、点検又は修繕に支障をきたすような物件を置き又は工作物を設置してはならない。
2 物件又は工作物の設置によりメーターの点検若しくは修繕が著しく困難である場合は、企業長は当該メーターの位置を変更することができる。
(メーターの点検)
第20条 企業長は、メーターを点検したときは、その都度使用水量を記載した書面により、給水を受ける者に通知する。
(受水タンクに接続する装置)
第21条 条例第19条第3項の規定により、企業団のメーターを設置する受水タンクに接続する装置に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施工するものとする。
2 前項に規定する工事の設計又は施工は、給水装置工事の設計又は施工に準じて行うものとする。
3 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(私設消火栓の使用)
第22条 条例第22条第1項に規定する消防演習の時間は、10分を越えることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
2 消火栓使用後の封かんは、企業長が行う。
(修繕の依頼)
(給水装置等の検査の請求)
2 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。
(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) その他通常の検査以外で特別の費用を要するとき。
(給水申込納付金に係る給水管の口径)
第25条 条例第33条第3項の規定により給水申込納付金の額を算定する場合において、当該給水装置が異なる口径の給水管で構成されているときは、当該給水装置に係る給水管の口径は、当該給水装置に設置するメーターの口径と等しい口径の給水管の口径として条例別表第3を適用する。
(公共団体及び開発事業者等の納付金相当額)
第26条 条例第33条第5項に規定する納付金相当額は、次の各号に掲げる方法により計算した額とする。
(1) 既に造成された開発地については、それぞれの給水装置ごとに計算して得た納付金の合計額
(2) 造成しようとする開発地については、公共団体及び開発事業者等から提出された計画区画数及び各区画に設置する給水装置の予定口径に基づき、それぞれの給水装置ごとに計算して得た納付金の合計額
2 前項第2号の場合、著しく計画を変更したときは、前項第1号の規定により計算し追徴又は還付するものとする。
(私設消火栓の給水申込納付金)
第27条 条例第4条第3号に規定する私設消火栓の給水申込納付金は、これを免除するものとする。
(料金、手数料又は納付金の減免申請)
(給水装置の確認申請)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第29条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(届出の様式)
第30条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 条例第21条第1項第1号の届出 給水契約解除届(様式第9号)
(3) 条例第21条第1項第2号の届出 用途変更届(様式第10号)
(4) 条例第21条第1項第3号の届出 私設消火栓消防演習使用届(様式第11号)
(5) 条例第21条第1項第4号の届出 消防用使用届(様式第12号)
(6) 条例第21条第1項第5号の届出 住所(氏名)変更届(様式第13号)
(7) 条例第21条第1項第6号の届出 管理人変更届(様式第14号)
(8) 条例第21条第2項第1号の届出 給水装置所有者変更届(様式第15号)
(9) 条例第21条第2項第3号の届出 給水装置廃止届(様式第16号)
(水道使用者標識の掲示義務)
第31条 給水装置の所有者は、門戸等の見易い場所に企業長の交付する水道使用者標識を掲示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月10日規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の八匝水道企業団給水条例施行規程の規定により調製した用紙は、この規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成10年9月1日規程第6号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年2月7日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規程第10号)
(施行期日)
この規程は、公示の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
附 則(平成17年1月11日規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年5月16日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の八匝水道企業団給水条例施行規程によつてなされた申込の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、改正前の様式の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年3月19日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の八匝水道企業団給水条例施行規程の規定により調製した用紙は、この規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
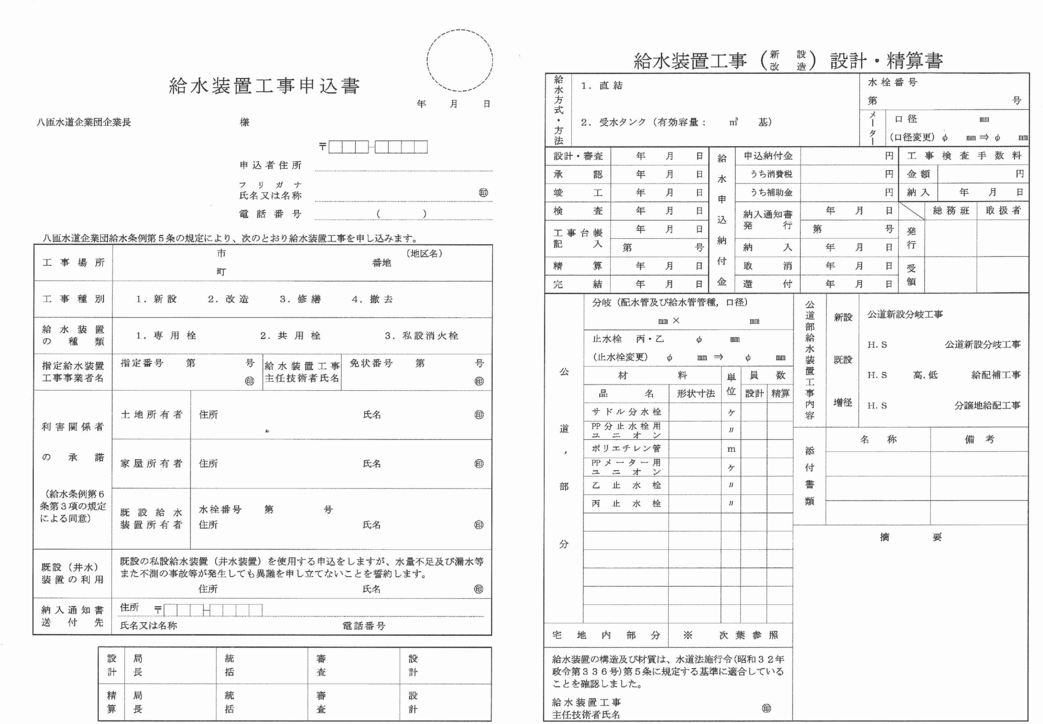
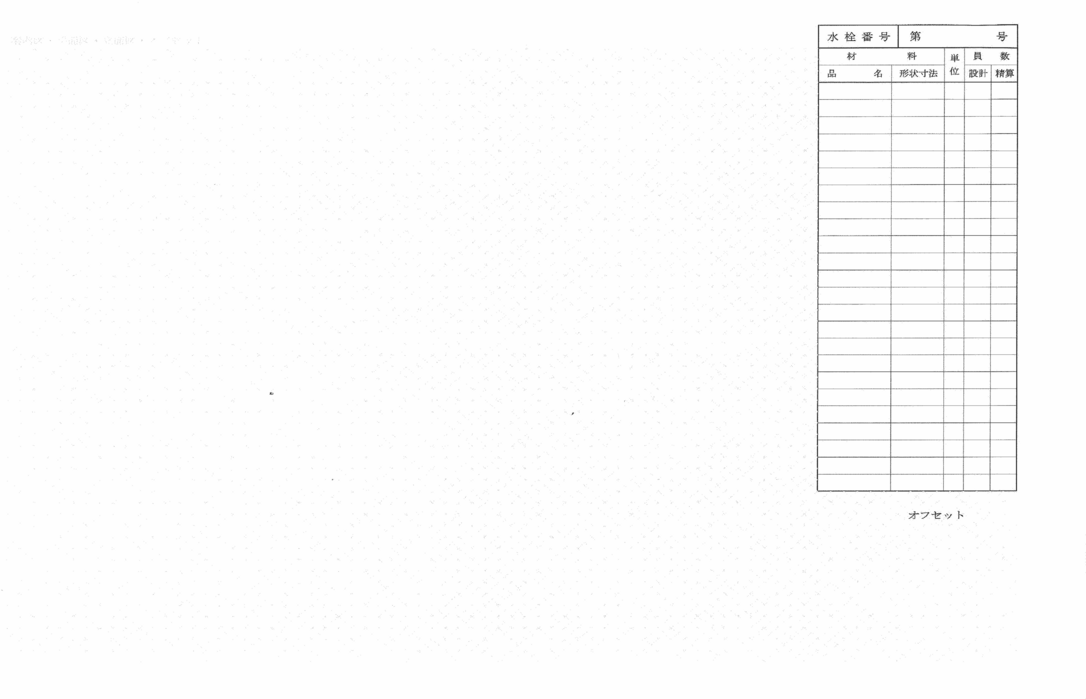
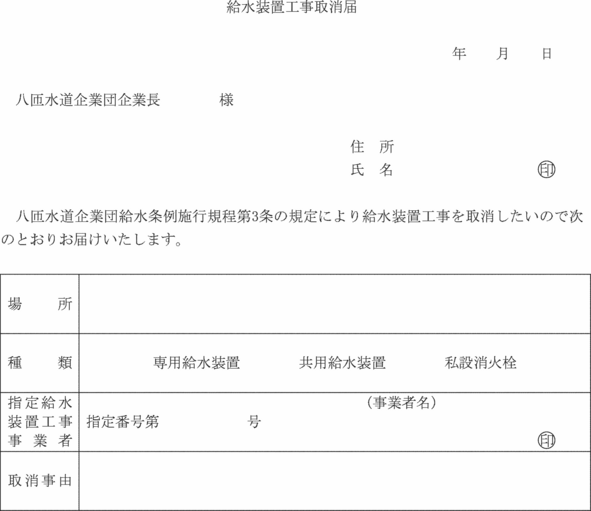
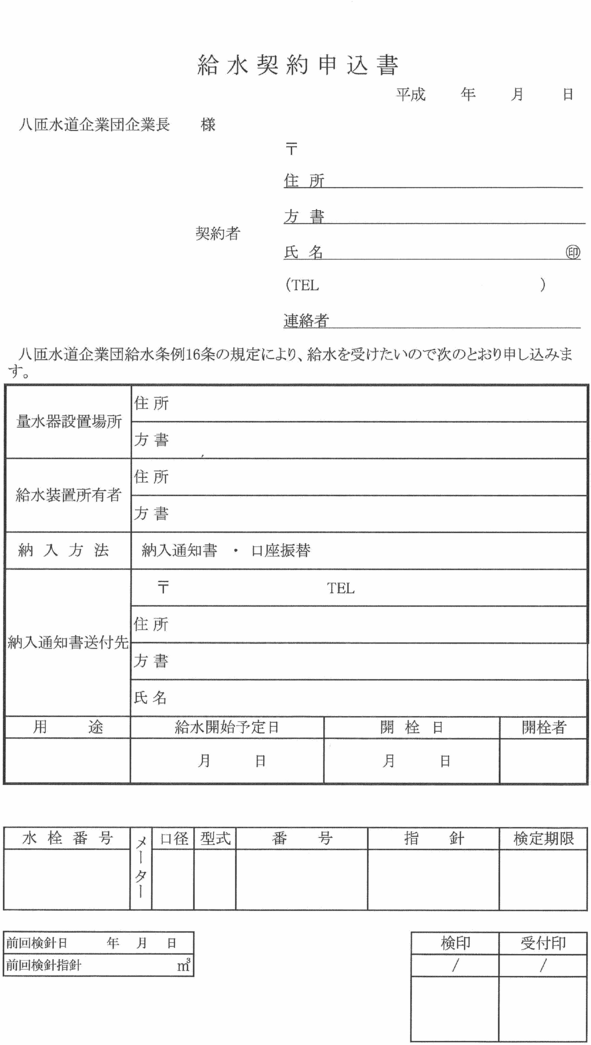
様式第4号 削除